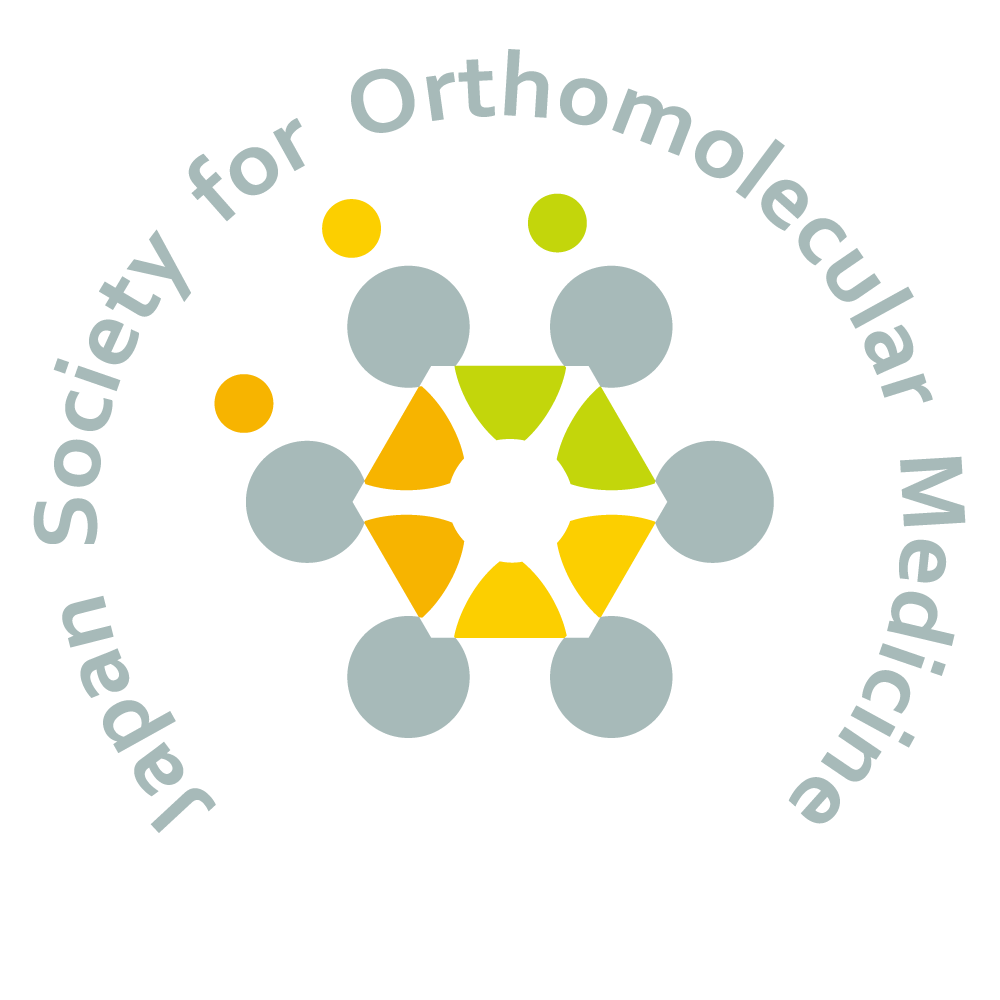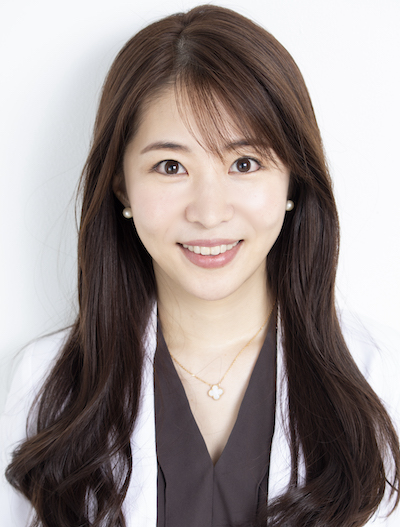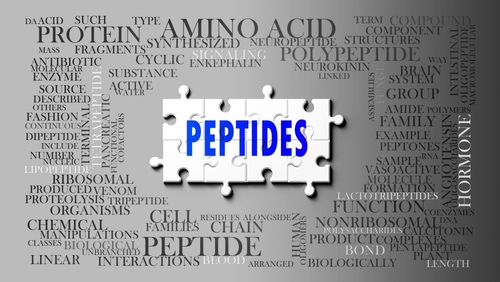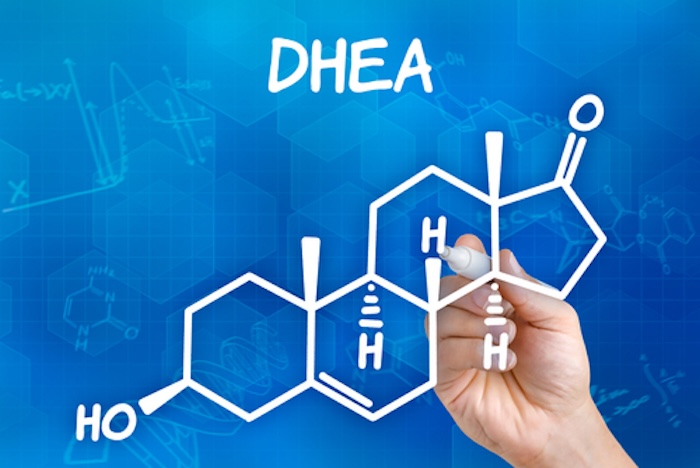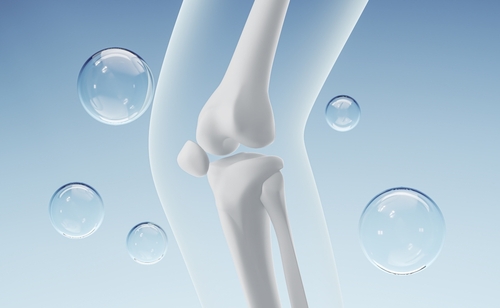内因性オピオイドペプチドの1つであるメトエンケファリンは、がん細胞のオピオイド成長因子-OGF受容体に結合し活性化することで機能します。具体的には、鎮痛効果、特に神経因性疼痛を抑制し、胃腸筋の収縮を抑制します。また、さまざまな免疫細胞に存在するデルタオピオイド受容体の活性化により、免疫系を調節し炎症誘発性サイトカインの分泌や白血球の増殖を抑制する効果があります。
- 個別の病気
- 治療法・栄養
がん治療の新たな一手~がん治療薬としてのペプチド~
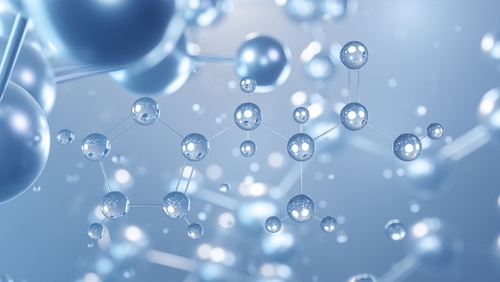
今回は前回ご紹介したペプチド療法のがん治療への応用の可能性についてまとめていきたいと思います。
ペプチド療法についてまとめた記事を読まれていない方のために簡単に復習すると、ペプチドとは、アミノ酸が2~50個つながった分子で、51個以上つながったものはタンパク質と呼ばれます。ペプチド薬は、従来の低分子化合物からなる医薬品と比較して効果が高く副作用が少ない、またもっと高分子のバイオ医薬品と比較して安価であるというメリットがあり、次世代の医薬品として注目されています。
市場にすでにあるペプチド薬としては、糖尿病薬や肥満薬として人気のあるGLP-1受容体作動薬やインスリンなどがあり、効果の高さや安全性を実感していただけるかと思います。特にGLP-1受容体作動薬は、人類の寿命を伸ばす可能性をもつ薬として大変期待されており、次世代のメトホルミンとして注目されています。ペプチド薬で期待できる効果としては、以下のようなさまざまな効果があります。
- 炎症の抑制
- 老化の逆転
- 減量
- 怪我からの治癒の促進
- 体脂肪の減少と、筋肉の成長
- パフォーマンスの向上
- 関節痛の緩和
- 軟骨、筋肉、神経の再生
- 性的欲求の改善
- 髪、肌、爪の質の改善 他
また使用するペプチドの種類によって、注射やカプセル、クリーム、点鼻スプレーなど、それぞれふさわしい投与方法で行います。
このように多様な働きをもつペプチド薬ですから、当然がん治療にもその応用が行われています。今回はその中から3つのペプチド薬と、実際の症例についてご紹介します。
内因性オピオイドペプチド
さらにOGF軸は、正常細胞やがん細胞の細胞増殖を制御することから、メトエンケファリンもがん細胞の増殖を抑えつつ、強力な免疫ブースターとして機能する可能性があると報告されています。特に、肝芽腫や乳がん、結腸がん、腎がん、卵巣がん、膵がん、黒色腫、またがん以外でも自己免疫性脳脊髄炎や多発性硬化症などではOGF軸の調節が重要なことが知られています。
がん治療としても非常に歴史がある低用量ナルトレキソン(LDN)も、実際には内因性エンケファリンレベルを増加させることによって機能します。つまりメトエンケファリンも LDN の代替品としても使用できると考えられています。ただし難点としては、体内での分解速度が早いことから1日2回の皮下注射が必要です。
また、実際に化学療法で効果がなかった進行性の膵がん患者さん24名にメトエンケファリンを投与した臨床試験では、臨床的利益が化学療法などより良く、また生存期間も未治療の3倍と改善が示唆されました。
チモシンαー1
チモシンα-1は、胸腺に存在するペプチドの一部で胸腺ペプチドなどと呼ばれたりします。胸腺は免疫系を調節する役割を担う臓器で、チモシンα-1は、がんや細菌・ウイルスに感染した自分の細胞を探し出し、破壊する役割をもつキラーT細胞や、そのキラーT細胞やB細胞などに指示を出して攻撃させるヘルパーT細胞などの働きを調節したり増強したりすることで効果を発揮すると考えられています。たとえば、抗菌作用や抗ウイルス作用、また抗真菌作用、ワクチンの効果を高める作用、がんの増殖を抑制や予防し、健康状態を改善する作用を期待して処方されます。
実際アメリカでは「ザダキシン」という商品名でFDAに承認され、医薬品として使用されています。さまざまなタイプのがんやウイルス性疾患に対して広く使用、研究されており、一部の医師は、慢性疲労やライム病、自己免疫性疾患にもチモシンα-1を使用しています。
去年、韓国の統合医療のクリニックをいくつか見学した際も、その全ての統合医療のクリニックで、がんの患者さんへチモシンα-1が処方されていました。
チモシンα-1は、非小細胞肺がん(NSCLC)、悪性黒色腫、肝細胞がん(HCC)、乳がん、非ホジキンリンパ腫、結腸直腸がん、頭頸部がん、白血病、膵臓がん、腎細胞がんなどさまざまな種類のがんを患う1000人を超える患者さんを対象とした臨床研究で、免疫学的パラメーターを改善し、腫瘍の反応率を高め、生存率と生活の質を改善することが示されています。
チモシンα-1はメトエンケファリンほどではありませんが、週2回皮下注射する必要があるお薬です。
膜活性抗がんペプチド
PNC-27という暗号のような名前のペプチドは、がん細胞の細胞膜にあるHDM-2というタンパク質に結合し、がん細胞の細胞膜に穴をあけることで細胞死を引き起こすペプチドです。正常細胞ではこうした反応は起こさないため、がん細胞だけを狙い撃ちすることができます。PNC-27は、膵がん、乳がん、白血病、黒色腫、その他のがん株を含む、さまざまながんに効果的であることが示されています。
GHKペプチド
GHKは、グリシン-ヒスチジン-リジンからなるトリペプチドで、人の血漿や唾液、尿中などに自然に存在するペプチドです。若い頃にはたくさんありますが、老化と共に減少してしまい、それにより再生能力の低下を引き起こすと考えられています。
アンチエイジングの領域では、創傷治癒や育毛、皮膚の引き締めなど美容の目的で使用されることが多いペプチドですが、がん患者さんで過剰発現する遺伝子の70%でRNA産生を抑制したり、遺伝子活性のリセット、またがん細胞で失われているアポトーシスのシステムを再活性化したりすることなどから、がん治療でも効果が期待されています。
以上のようなペプチドを組み合わせて使用することもできます。以下は自分で経験した症例ではありませんが、アメリカの医師が講義で発表されたケースを2例ご紹介します。
ケース1
ステージ4の結腸がん、多発肝転移、多発肺転移の80歳男性の患者さんは、主治医から予後は3カ月でもう治療ができないと言われ、ペプチド療法を行う先生のクリニックを受診しました。
チモシンα-1を10日間連続投与した後、週に2回に、またメトエンケファリンの点滴を週2回(8週間)と、最初の3カ月間はGHKを週3回投与したところ、6カ月後にがんが縮小し、その後3年間がんの大きさに変化なく縮小を維持し、普通の生活を送っているそうです。
ケース2
72歳の男性患者さんはステージⅢbのB細胞リンパ腫と診断され、化学療法を行う前にメトエンケファリンの治療を週に1回、計2回、またチモシンα-1を10日間連続で、その後週2回で継続して受けたところ、2カ月で検査値は正常化し、4カ月でがんが消えたと主治医から言われました。主治医は患者さんに、自分の30年の経験上、最も早くがんが消えた患者であると言い驚いていたそうです。
おわりに
このようなさまざまなペプチド薬も、今やアメリカなどの国々と同様に日本でも使用することができます。これらは輸入薬であることから輸入にかかるコストや、円安とインフレの影響で少し値段はしますが、ぜひ少しでもこのような良い治療が認知され、日本の患者さんの力になってくれれば良いなと思います。
※本記事は『統合医療でがんに克つVOL.187 (2024年1月号)』にて掲載された「リオルダンクリニック通信54」の許可を得た上で一部調整したものです。
前田 陽子 (マエダ ヨウコ)先生の関連動画
同じタグの記事を読む