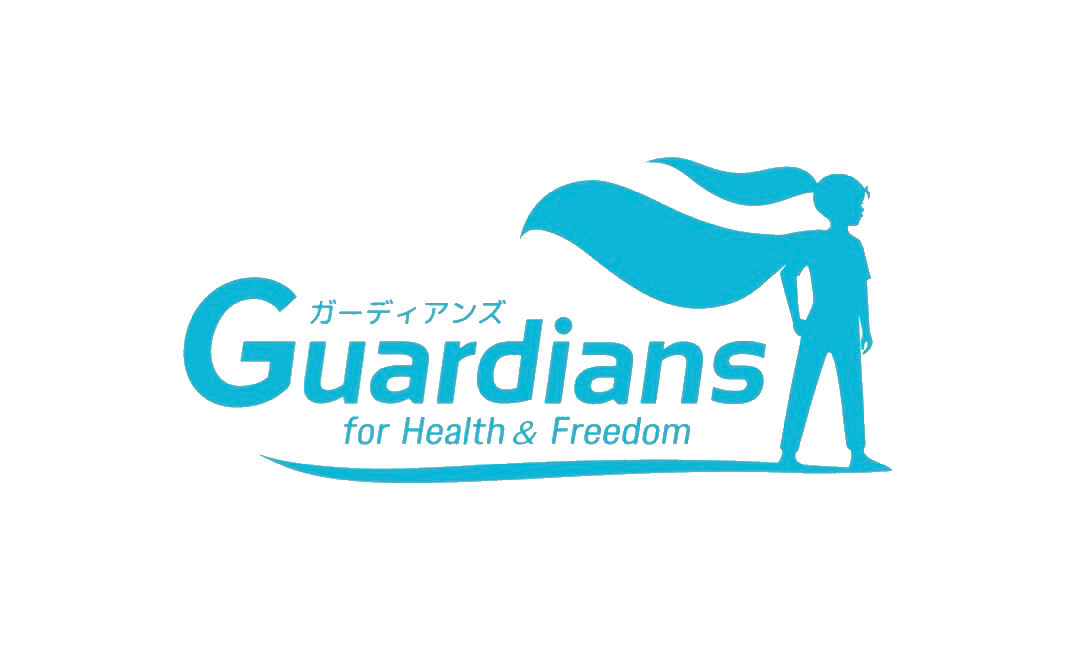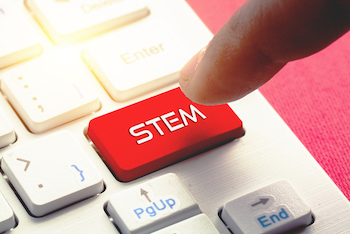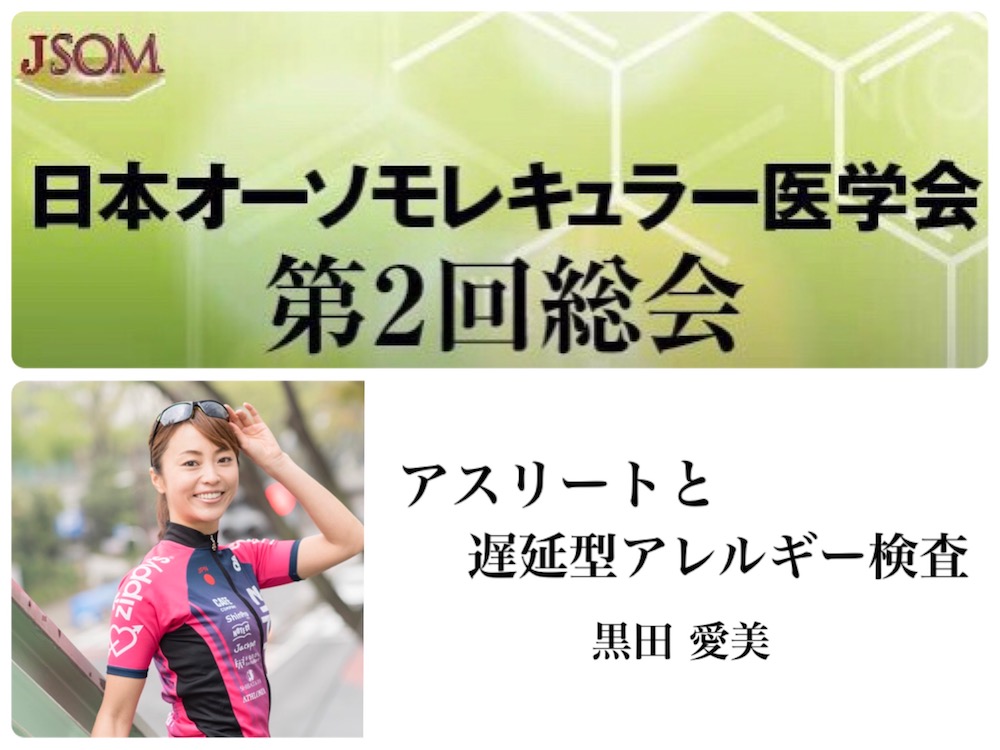寒暖差アレルギーは、医学的には血管運動性鼻炎と診断される場合があります。主な症状は以下のようなものです。
- 悩み・目的
寒暖差アレルギーとは?その症状と対策を解説

季節の変わり目、特に秋が深まる頃になると徐々に気温が下がり始め、日中と夜の気温差も激しくなってきます。
朝晩に咳や鼻水が出るなどの不調を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。それは、「寒暖差アレルギー」の可能性があります。この記事では日本オーソモレキュラー医学会会長の柳澤 厚生先生に監修いただき、寒暖差アレルギーの症状や具体的な対策についてご紹介いたします。
寒暖差アレルギーの症状
- 鼻水や鼻づまり
- くしゃみ、咳
- 蕁麻疹、かゆみ
- 食欲がなくなる、胃腸の痛み
風邪の症状にも似ているため、「ただの風邪?」と片付けてしまいがちですが、実は寒暖差アレルギー症状の可能性もあるのです。何となく体調が優れない状態が続く場合は、是非早めにお近くの医療機関に相談してみることをおすすめします。
寒暖差アレルギーの原因とは
寒暖差アレルギーは、寒暖差が激しいことによって自律神経が乱れることで生じます。血管は寒いと縮み、暑いと広がります。しかし温度差が激しくなると、この血管の収縮が環境に追い付けず、自律神経に不調をきたしてしまうのです。特に7度以上の気温差がある時には症状が出やすいと言われています。
風邪の場合はウイルスに、花粉症などのアレルギーの場合はアレルゲンに影響されて生じますが、寒暖差アレルギーはこれらに関係ありません。つまり、アレルゲンを取り除くなどの対処ができないので、日々の生活の中で予防と対策を心がけることが重要になります。
寒暖差アレルギーは予防できる?

それでは「寒暖差アレルギーかも?」と思った時、どう対処したらいいのでしょうか。まずは毎日の生活の中で体調管理をしていくことが大切です。
体力をつけましょう
寒暖差アレルギーは、筋肉量の少ない高齢者や女性に多いとされています。日々の生活の中で、体力をつけるための簡単な運動を取り入れていきましょう。30分のウォーキングからでも、基礎代謝を上げるためには効果があると言われています。
体をなるべく冷やさないようにしましょう
温度差が激しいと症状が出やすくなるので、寒い日には体をなるべく冷やさないように心がけることが大切です。例えば、外出時にはマスクやひざ掛けを持ち歩くのも良いでしょう。血流をよくするために、特に足首や首周りを冷やさないようにするのも効果的です。
入浴時はシャワーではなくお風呂に浸かる
湯船にしっかりと浸かることで、身体の芯から温めることができると同時に、自律神経を整える効果も期待できます。忙しくても毎日湯船に浸かるようにしましょう。
食生活での予防法とは〜栄養療法の観点から〜

食事の面では、まず3食しっかり摂ることが大切です。「忙しいから、つい朝食を抜いてしまう」という方もいるかもしれませんが、特に朝は低体温になりやすいため、必ず食事を摂るようにしましょう。次に、特に摂取することがおすすめの食材・栄養素をご紹介します。
身体のエネルギーを作る「たんぱく質」
三大栄養素の1つとして、人が生きていく上で重要な栄養素であるたんぱく質。身体を動かす原動力にもなるため、しっかりと摂取しておきたいものです。
<たんぱく質を多く含む食品>
- 肉類(牛・豚・鶏など)
- 魚介類(魚・小魚・貝など)
- 卵類
- 大豆や乳製品
疲労回復にも効果あり「ビタミンB群」
たんぱく質をエネルギーに変える役割を持つ「ビタミンB群」も合わせて摂取しましょう。特にビタミンBは、長期間身体にとどめておけないため、こまめな補給がポイントになります。また、ビタミンB1やB2には疲労回復効果も期待できます。B1はうなぎや豚肉、B2はレバーや卵、納豆に豊富に含まれています。
冷えた身体を内側から温める食材
入浴などで身体を温めることも大切ですが、身体の中から温めることも大切です。生姜は身体を温めてくれる食材として有名ですが、生姜以外にも身体を温めてくれる食材は多くあります。下記を参考に、日々の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
- 生姜
- ネギ
- にんにく
- 唐辛子
- 玉ねぎ
- かぼちゃ
- 鶏肉
- アジ
- サバ
まとめ
いかがでしたか?「私の不調、もしかして寒暖差アレルギーかも!」と思った時は、今回ご紹介した対策を是非試してみてくださいね。風邪との区別が付かずわからない場合は、病院で診断してもらうことをおすすめします。
また、日々の食生活の改善が難しい場合は、サプリメントや点滴から各栄養素を補充することも可能なので、その際には栄養療法に詳しい先生に相談してみましょう。
日本オーソモレキュラー医学会に所属されている先生は、こちらのサイトで検索できます。
柳澤 厚生 (ヤナギサワ アツオ)先生の関連動画
同じタグの記事を読む
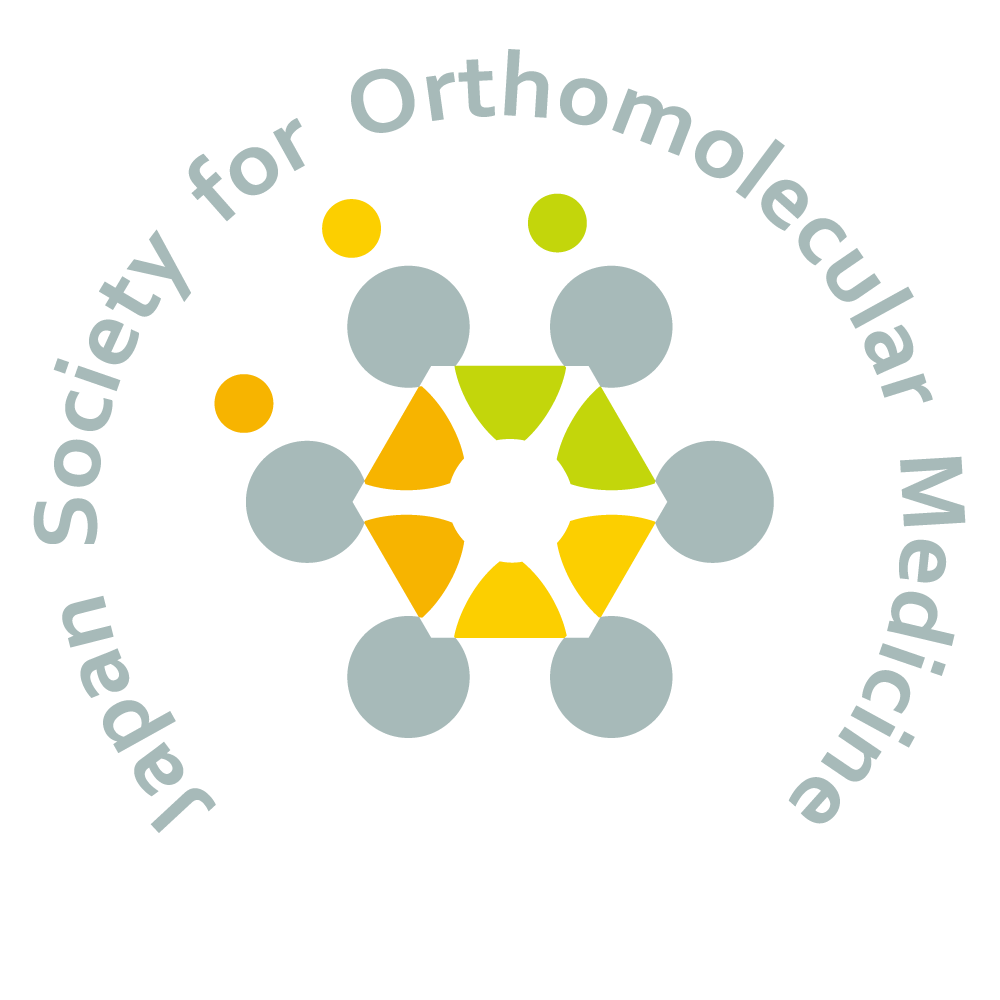

のコピー1.jpeg)