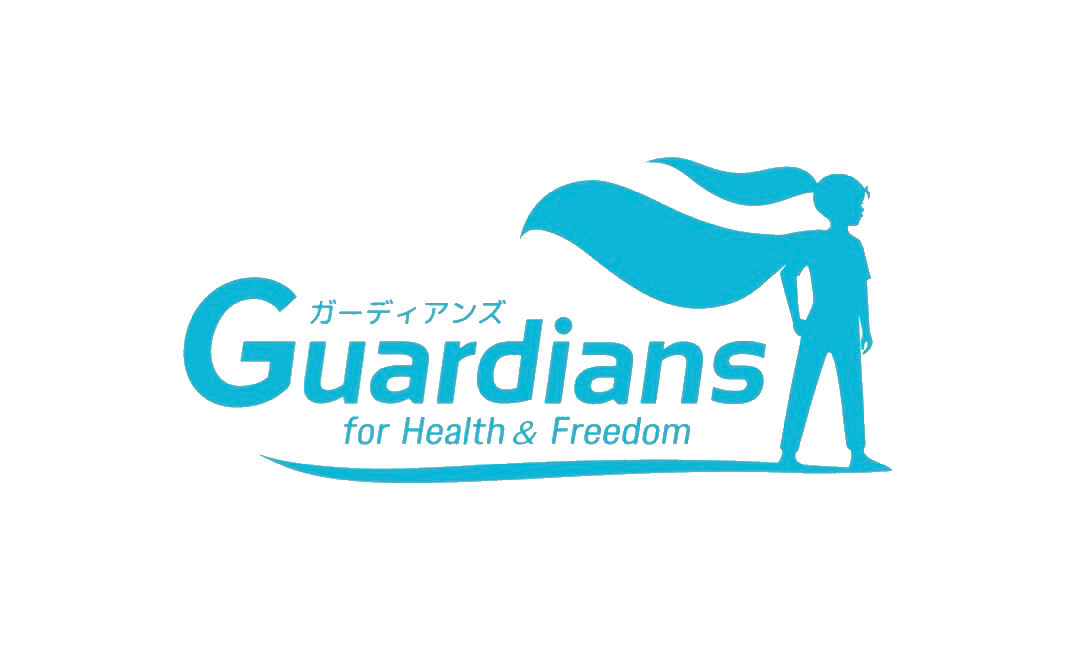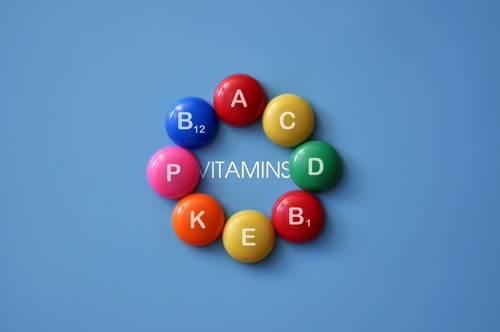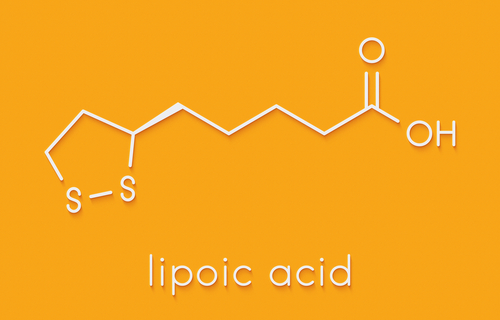<写真>ハイブリッド・オーソモレキュラー・プロトコルを提唱した国際オーソモレキュラー医学会会長のイルイエス・バグリ医師
ミトコンドリアと幹細胞を標的としたがん治療アプローチ:ハイブリッド・オーソモレキュラー・プロトコル

がんの治療は外科手術、化学療法、放射線治療など、腫瘍を物理的に取り除くことや、がん細胞を破壊することを目的としています。しかし、治療後の再発や転移といった課題は依然として残されており、がん克服の道筋は未だ確立されていません。
現在の標準的ながん治療法は、主にがん細胞のDNA変異を標的としています。しかし、これらの治療法は、がん幹細胞やミトコンドリア機能の改善を直接的に目指していないため、治療効果が一時的にとどまるのが現状です。例えば、化学療法や放射線治療は、腫瘍の大部分の細胞を効果的に排除しますが、がん幹細胞に対しては効果が限定的です。そのため、がん幹細胞が残存すると再発や転移が避けられません。これらの治療法は酸化的リン酸化の機能を回復どころか、むしろその機能をさらに悪化させる可能性があります。
このような現状の中で新しい治療概念として注目されているのが「ミトコンドリアと幹細胞の関連(Mitochondrial-Stem Cell Connection, MSCC)」理論です。
本稿では、MSCC理論に基づく「ハイブリッド・オーソモレキュラー・プロトコル」と呼ばれる新たな治療アプローチについて解説します。分子栄養療法、既存薬、食事療法、補助療法を組み合わせた多面的なアプローチで、がん治療における新たな道を切り開く可能性を秘めています。このプロトコルは、2024年に国際オーソモレキュラー医学会のイルイエス・バグリ会長(写真)ら世界各国の15人の専門家による共同提言としてオーソモレキュラーメディスン誌に発表されました。
■MSCC理論とは何か

MSCC理論は、がんの発生、進行、転移における幹細胞とミトコンドリアの機能不全の重要性を指摘しています。この理論は、がん幹細胞理論と代謝理論を統合したものであり、従来のDNA変異説に基づく体細胞突然変異理論とは一線を画しています。この理論は次の三点に注目しています。
1.ミトコンドリアの機能とがんの関係
ミトコンドリアは細胞内でエネルギーを生成する主要な細胞小器官であり、酸化的リン酸化はその中心的なプロセスです。しかし、幹細胞におけるミトコンドリアの機能不全は、がん幹細胞(CSCs)の形成を引き起こし、腫瘍形成の一因となります。この機能不全は、がんの初期段階から進行、転移に至るまで重要な役割を果たすとされています。
2.がん細胞のエネルギー代謝
がん細胞は正常な細胞とは異なり、エネルギー源として主にグルコースとグルタミンを利用します。この代謝パターンは、ミトコンドリアでの酸化的リン酸化の代わりに解糖系やグルタミン分解が優先される「ワーバーグ効果」として知られています。これらの代謝特性が、がん細胞の増殖と治療抵抗性を助長します。
3.腫瘍微小環境の変化
ミトコンドリア機能不全によって引き起こされる腫瘍微小環境の変化(低酸素状態、酸性化など)は、がん細胞の成長と転移を促進、がん治療の難しさを増大させる一因となります。
■ハイブリッド・オーソモレキュラー・プロトコルの詳細
バグリ医師らのチームはMSCC理論に基づき、ハイブリッド・オーソモレキュラー・プロトコルを提唱しています。このプロトコルは、①ミトコンドリア機能の回復、②がん幹細胞(CSCs)の抑制、③がん細胞のエネルギー供給遮断により、がん細胞の成長を効果的に阻止します。プロトコルは個々の患者の状態に応じて調整されます。通常は12週間を基準とし、治療期間中は、血液検査や症状のモニタリングを行い、必要に応じてプロトコルを修正します。プロトコルは以下の4つの柱からなります。
1.分子栄養療法
オーソモレキュラー療法では、以下の栄養素が重要視されています。
①ビタミンC:ビタミンCは、がん細胞に酸化ストレスを与え、細胞死を誘導します。高濃度ビタミンC点滴1.5g/kgを週2〜3回の投与は、がん幹細胞や転移の抑制に有効です。
②ビタミンD:ビタミンDは、ミトコンドリアの機能を改善し、腫瘍の進行を抑制します。また、ビタミンD欠乏は多くのがんと関連し、適切な補充が治療効果を高めます。ビタミンDの補充は血中濃度80ng/mLを目標とします。
③亜鉛:亜鉛はミトコンドリアの保護や細胞代謝の正常化に寄与します。全てのステージのがんに亜鉛を1mg/kg/日を投与します。
2.既存薬の活用
既存薬の新たな用途での活用は、ハイブリッドプロトコルの中核を成しています。
①イベルメクチン:抗寄生虫薬として知られるイベルメクチンは、がん細胞の成長を抑制し、特にがん幹細胞に対して効果を発揮します。低グレードのがん:0.5mg/kgを週3回、中グレードのがん:1mg/kgを週3回、高グレードのがん:1〜2mg/kg/日を投与する。
②メベンダゾール:がん細胞の微小管形成を阻害し、細胞分裂を抑制します。また、化学療法耐性を持つがん細胞にも有効です。メベンダゾールは低グレードのがん: 200mg/日、中グレードのがん: 400mg/日、高グレードのがん: 1,500mg/日を投与する。
③DON(6-diazo-5-oxo-L-norleucine):DONは、グルタミン代謝を特異的に阻害し、がん細胞のエネルギー供給を遮断します。静脈内または筋肉内で0.2〜0.6mg/kg/日、経口で0.2〜1.1mg/kg/日投与する。
3.食事療法
①断食(ファスティング)は、がん細胞のエネルギー代謝をリセットし、ミトコンドリア機能を回復させます。
②ケトジェニックダイエット(低炭水化物・高脂肪食、900〜1500kcal/日)は、がん細胞が利用できるエネルギー源を制限し、腫瘍の成長を抑制します。
4.補助療法
①高気圧酸素療法(HBOT):HBOTは、がん細胞の低酸素環境を改善し、酸化ストレスを引き起こすことで腫瘍を抑制します。
②身体活動:適度な運動は、ミトコンドリアの機能を強化し、がん細胞の成長を抑制します。
■プロトコルの安全性
ハイブリッドプロトコルに使用される成分や薬剤の多くは、既に安全性が確認されているものです。例えば、高濃度ビタミンC点滴は、がん患者において安全性が高いことが証明されています。また、イベルメクチンやメベンダゾールなどの薬は、通常の医療用途で長年使用されてきた薬剤であり、その安全性プロファイルが確立されています。
一方で、プロトコルを実施する際には、患者の個別の状況に応じた注意が必要です。特に、高用量の栄養素や薬剤の投与には、医師の監督の下で血液検査などを行いながら適切なモニタリングが求められます。
■プロトコルの今後の課題と展望
ハイブリッド・オーソモレキュラー・プロトコルは、がん治療の新たな可能性を提示する画期的なアプローチです。しかし、これを臨床現場に広く普及させるためには、さらなる研究が必要です。具体的には以下の課題があります:
1.ランダム化比較試験の実施
プロトコルの有効性と安全性を従来の治療法と比較するためには、大規模な臨床試験が必要です。
2.患者ごとの最適化
各患者のがんの種類や進行度に応じて、プロトコルの成分や用量を調整するためのガイドラインの確立が求められます。
3.コストとアクセス
特に再利用薬や特殊な食事療法、高気圧酸素療法などは、現時点ではコストや入手の難易度が高い場合があります。これを克服するための仕組みづくりが重要です。
■おわりに
ミトコンドリアと幹細胞の関連(MSCC)理論に基づくハイブリッド・オーソモレキュラー・プロトコルは、がん治療における革新的な戦略として注目されています。このプロトコルは、ミトコンドリア機能の回復、がん幹細胞(CSCs)の排除、がん細胞のエネルギー供給経路の遮断を目指した多面的なアプローチです。プロトコルが持つ可能性は非常に高いと言えます。今後、さらなる研究が進むことで、このアプローチががん治療の標準となり、多くの患者に希望をもたらす日が来ることを期待しています。患者にこのプロトコルを適用する場合には必ず論文原著で詳細を確認してください。
<参考文献>
Baghli I, et al. (2024) Targeting the Mitochondrial-Stem Cell Connection in Cancer Treatment: A Hybrid Orthomolecular Protocol(がん治療におけるミトコンドリアと幹細胞の関連を標的としたアプローチ:ハイブリッド・オーソモレキュラー・プロトコル). J Orthomol Med. 39.3
柳澤 厚生 (ヤナギサワ アツオ)先生の関連動画
同じタグの記事を読む
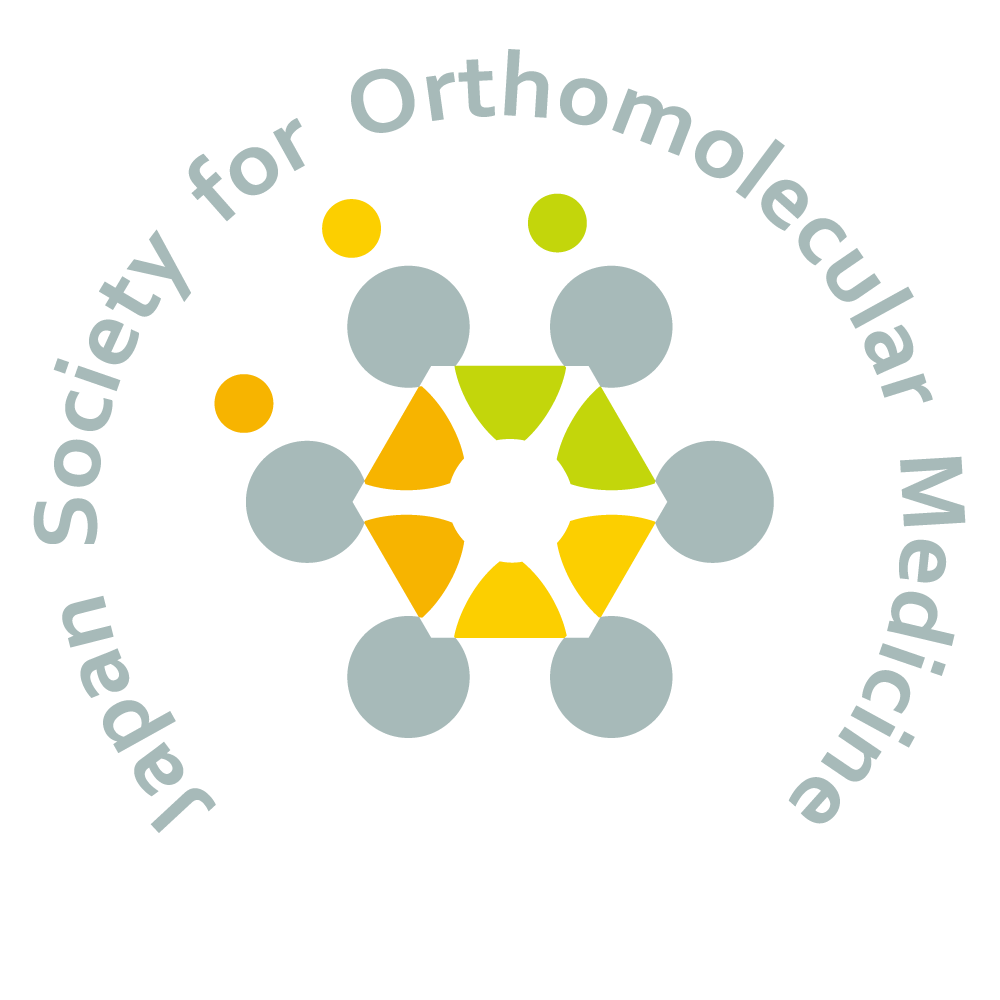

のコピー1.jpeg)