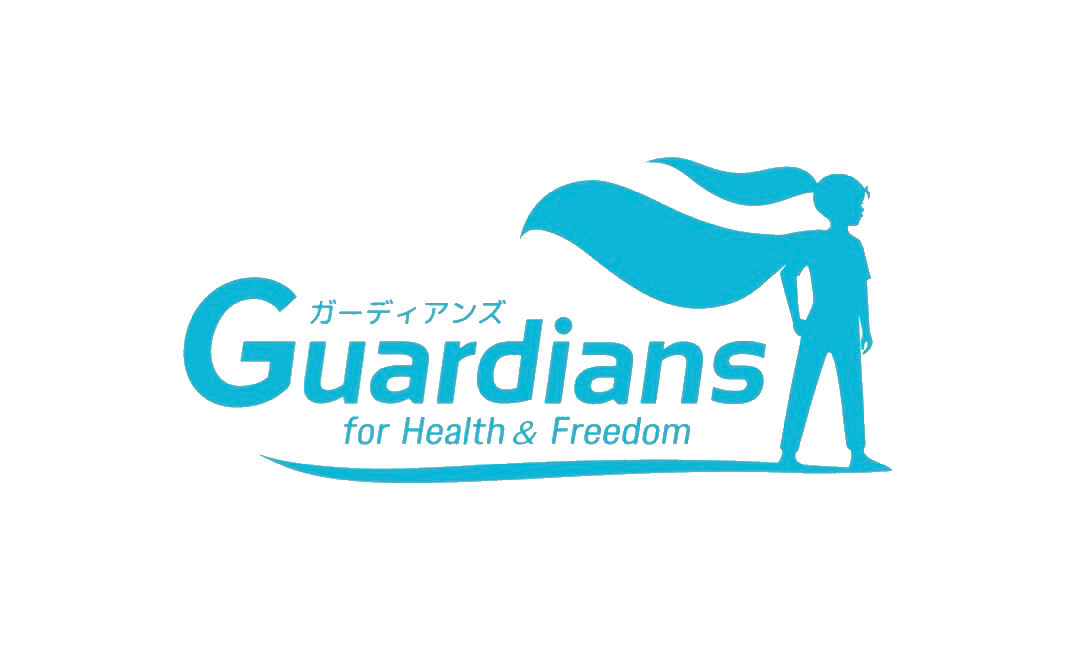「インフルエンザ」とは、どういった病気なのでしょうか。インフルエンザには、インフルエンザウイルスに感染することで発病します。インフルエンザウイルスには、大きく分けてA型・B型・C型の3つのタイプが存在します。また、2000年以降には鳥インフルエンザや豚インフルエンザなど、新型インフルエンザと呼ばれるものが流行し、話題になりました。
- 個別の病気
インフルエンザ予防に必要な5つの栄養とは?

だんだんと気温が下がってくると、気になるインフルエンザ。風邪よりも高熱が出るケースが多く、悪化したり、肺炎などの合併症を起こすと、命の危険もあります。ただでさえ体調を崩しがちな冬に、できればかかりたくないですよね。
小児の発症数が多いので、自分の子供がインフルエンザにかからないか、心配しているお母さん・お父さんも多いのではないでしょうか?実は、日本だけでも年間1000万人が、季節性のインフルエンザにかかっているというのです!
インフルエンザを予防するためにできることとは、何でしょうか?この記事では、一般的に知られている方法に加え、オーソモレキュラー栄養療法の専門家の立場から、食事や栄養でインフルエンザを予防する方法をお伝えします。
そもそも「インフルエンザ」とは?
.png)
毎年11月後半頃から流行が始まり、1〜2月がピークと言われていますが、近年は異常気候の影響もあり、流行の期間は年によって少しずつ異なります。
インフルエンザの具体的な症状は?
症状としては、40℃近いような急な発熱、頭痛、のどの痛み、寒気、関節痛などに加え、吐気や下痢を伴うケースもあります。体力と免疫力がある人であれば1週間程度で回復しますが、子供やお年寄りでは悪化する場合があります。
子供(特に5歳以下)は、インフルエンザ脳炎・脳症、お年寄りの場合は、肺炎などの合併症を引き起こす可能性があり、最悪の場合は死に至るケースもあります。
発病してしまった場合はすぐに医療機関を受診すること、そして可能であれば発病を未然に防ぐことがとても重要です。
インフルエンザにかからないために!一般的な予防法は?
.png)
厚生労働省のウェブサイトでは、手洗い・うがい、そしてマスクをすることで感染を防ぐことを推奨しています。また、インフルエンザワクチンの接種も推奨されています。
ワクチンには、インフルエンザウイルスに感染したとしても、発症する確率を下げる効果、そして発症した場合の重症化を抑える効果が認められています。
しかし「インフルエンザワクチンは効かない、意味がない」といったような話を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。医者のなかでも、インフルエンザワクチンを勧める医者、勧めない医者がいるのが現状です。
なぜ?「インフルエンザワクチンは効かない」という説

冒頭にお話ししたように、インフルエンザには複数のタイプが存在します。インフルエンザワクチンは、その年の流行のウイルスタイプを予測して製造されるため、この予測が外れればワクチンの効果が低くなります。
もともと免疫力に自信がない人や、重症化する可能性がある子供・お年寄りは、摂取する価値があると考えていますが、最終的には患者さん自身が医師と相談し、判断することが必要になってきます。
また「ワクチンを接種すれば大丈夫!」と過信することなく、しっかりとオーソモレキュラー医学に基づいた栄養摂取を行い、日常生活の中で“インフルエンザにかからないカラダづくり”を行うことが、より重要になってきます。
インフルエンザワクチンに関しては、こちらの記事でも詳しく説明していますので、こちらもぜひご参照ください。
「5つの栄養」が、インフルエンザ予防のカギ!
では、インフルエンザの予防のためには、どのような栄養を取ればいいのでしょうか。また、食事では何に気をつければ良いのでしょうか。免疫力を高めると言われている栄養素にはたくさんの種類がありますが、すべて摂取しようとすると、きりがありません。
まずは、ここで述べる5つの栄養をしっかりと摂取して、流行シーズンの前からインフルエンザにかからないカラダづくりを始めましょう!
1.ビタミンD
.png)
「ビタミンDには免疫力を高め、あらゆる感染症の予防に役立つ」ということが、近年世界中の研究で明らかになってきました。日本の慈恵医大による研究では、ビタミンDのサプリメントを飲むことで、子供たちのインフルエンザ発症率が4割以上も減少したという結果も出ています。
また、肺炎の発症を予防するという研究結果も出ていますので、インフルエンザの発病だけでなく、インフルエンザになってからの重症化を防ぐ目的でも摂取すると良いと思います。
ビタミンDは日光に当たることで体内でも作られますが、冬は日射量が少なく肌の露出も減るので、不足しがちです。食材としては、イワシ、サバ、ニシン、サケなどの魚に多く含まれますので、インフルエンザが気になる季節には、食事に是非取り入れていきましょう。もちろんサプリメントでの摂取もおすすめです。
2.ビタミンC

「風邪を引いたらビタミンC」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。ビタミンCには免疫を高める効果や、炎症を抑える効果があるので、風邪・インフルエンザだけでなく様々な病気の予防・治療の効果が世界中で注目されています。
風邪の研究では、特に子供の場合、予防効果に加えて風邪を早く治す効果が高いという研究結果が出ています。柳澤先生のクリニックでは、風邪・インフルエンザ予防が目的であれば、患者さんには1日に1~3gの摂取を推奨しているとのことです。
サプリメントで一度にたくさん飲んでしまうと、吸収率が悪く、おなかの調子が悪くなってしまう人もいるので、何度かに分けて飲むか、もしくは吸収率の高いリポゾーム型のビタミンCサプリメントを推奨しています。
ピーマン、キャベツ、モロヘイヤなどの野菜類、かんきつ類やキウイフルーツなどの果物に多く含まれますが、水に溶けてしまうので、ゆで料理などは気を付けましょう。
3.ビタミンB群

肉や魚に多く含まれるビタミンB。忙しくなるとコンビニのパンやおにぎりで食事を済ませてしまう・・・というような人には不足しがちです。
特にうなぎや豚肉に多く含まれます。 ビタミンBには8種類あるのですが、それらをまとめて「ビタミンB群」もしくは「ビタミンBコンプレックス」と呼ばれます。
ビタミンB群は、肌や粘膜を強くする、脂質・糖質・タンパク質の代謝を助ける、疲労回復を助ける、精神の安定を助ける等、重要な役割がたくさんあります。
ビタミンBが粘膜を正常に保つことでインフルエンザのウイルスへの抵抗力が上がりますし、発熱によって体力が下がることを防いでくれるので、回復も早くなるでしょう。肉・魚をしっかりと食べること、そしてビタミンB群のサプリメントも積極的に取り入れましょう。
4.ビタミンA
.png)
ビタミンAには粘膜を強化する効果がありますので、インフルエンザウイルスへの抵抗力を高めることができます。鶏・豚・牛のレバーや卵、魚卵、ウナギなどに多く含まれています。
サプリメントも販売されていますが、ビタミンAは多く摂りすぎると吐き気や頭痛などの副作用が出るケースもあるので、基本的には食事で取れる範囲で問題ありません。逆に鶏・豚レバーには非常に含有量が多いので、食べる場合は週に一度程度が良いかと思います。
冬は、鼻腔や口・のどの乾燥が気になりますよね。粘膜が乾燥してしまうと抵抗力が落ち、ウイルスにかかりやすくなってしまいます。ビタミンAが不足しないように心がけると共に、マスクや加湿器を活用して、過度な乾燥を避けるようにしましょう。
5.乳酸菌や食物繊維

免疫力を高めるために、「腸」はとても重要な役割を担っています。体内の免疫細胞のうち、約6割が腸内に存在しています。そのため、腸内環境が悪くなってしまうと、免疫力が下がり、インフルエンザにもかかりやすくなってしまいます。

乳酸菌は腸内環境を整えるために必要不可欠。「乳酸菌といえばヨーグルト」と思う方も多いかと思いますが、確実に量を摂るためには、乳酸菌量が多いサプリメントを取り入れましょう。
また、発酵食品も乳酸菌が豊富なのでおすすめです。食物繊維は、腸内で乳酸菌のエサになります。乳酸菌の働きを助け、腸内環境を整えるために、食物繊維の多い野菜なども積極的に摂取しましょう。
まとめ 栄養療法でインフルエンザにならないカラダづくりを
いかがでしたか?手洗い・うがいだけでなく、食事やサプリメントで、家庭でもインフルエンザの予防ができるのですね。インフルエンザが流行する前から、しっかりと栄養を摂って、インフルエンザにかからないカラダづくりを始めましょう。
また、ビタミンなどの栄養素は、どれか一つだけをたくさん摂るよりも、色々な種類をバランスよく摂ることをお勧めしています。ここで挙げた5つ以外にも、ビタミンEやセレンなど、免疫力を上げてインフルエンザ予防に役立つ栄養素はたくさんあります。
免疫力を高める目的であれば、多種類の栄養素が含まれるマルチビタミンのサプリメントが良いでしょう。その場合は、医療機関でも取り扱われるような、質の良いサプリメントを選ぶことが重要です。徹底的にインフルエンザを予防したい場合は、栄養療法を専門としている医師や専門家に相談しましょう。
その他のインフルエンザ関連の記事はこちら
2018年(2017年度冬)のインフルエンザの傾向とは?
柳澤 厚生 (ヤナギサワ アツオ)先生の関連動画
同じタグの記事を読む
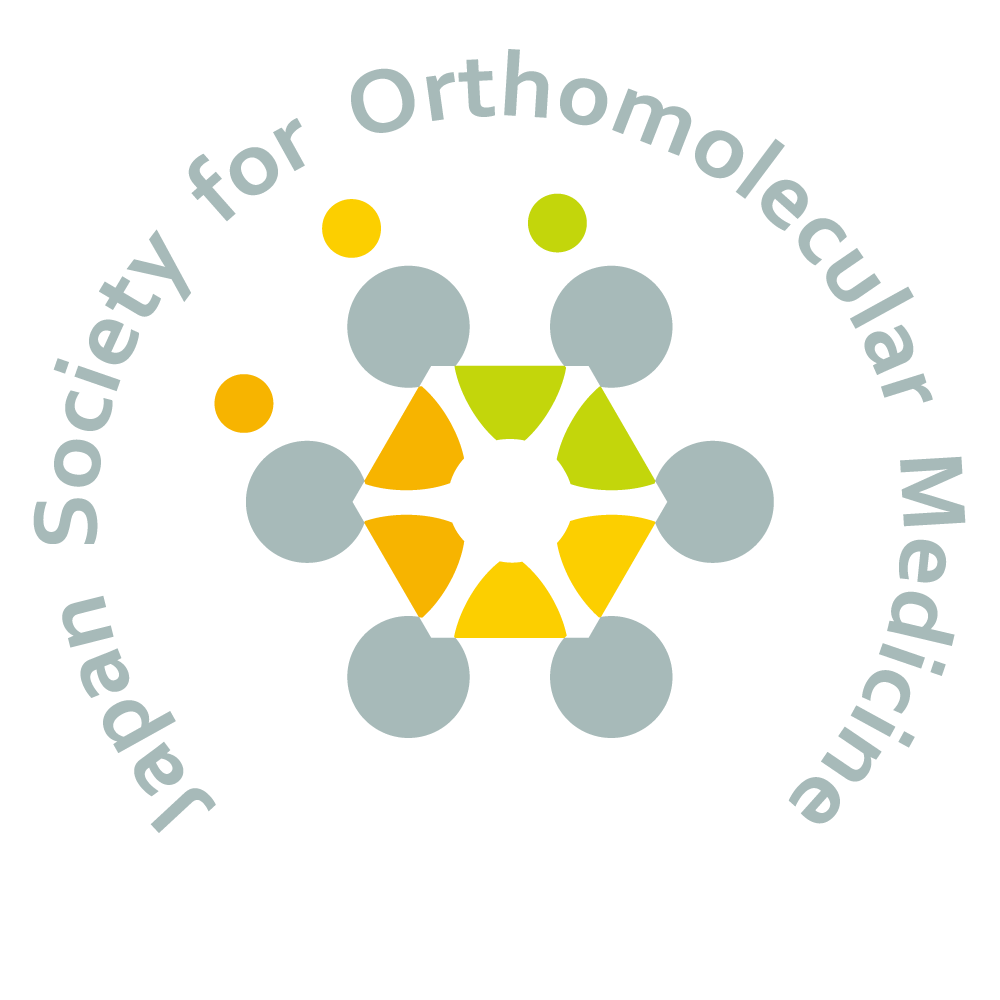

のコピー1.jpeg)