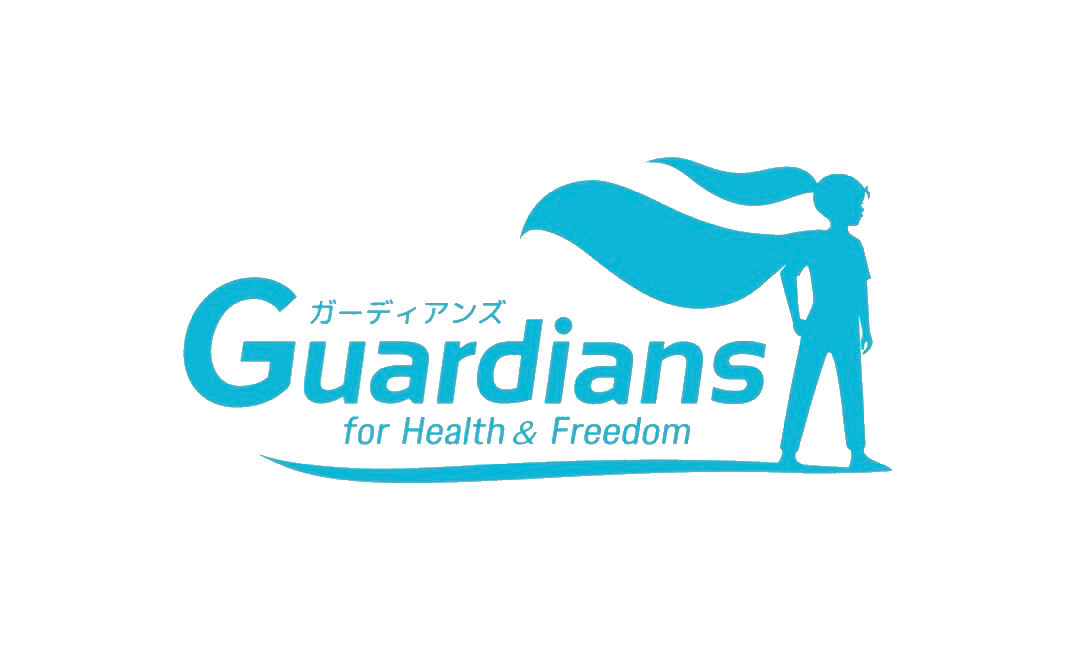マイコプラズマ肺炎とは、マイコプラズマ菌感染による主に子どもが発症しやすい肺炎の1つです。しかし大人や健康体の人であっても発症するリスクがあります。
風邪と同様、咳に含まれる細菌を吸い込むことによる飛沫感染と、食品についた細菌を口に入れること等による接触感染の2つが感染経路となります。
インフルエンザやノロウイルスほどの強い感染力はありませんが、1日のうち長い時間を過ごす家庭内での感染がおこりやすいため、家族が感染した際には特に注意が必要です。
- 個別の病気
マイコプラズマ肺炎の症状って?対策法とは?

厳しい寒さもおさまり、いよいよ春が近付いてきましたね。
インフルエンザなどの流行も落ち着き、花粉症でもないはずなのに「最近咳が止まらない・・・」「何だかだるさがとれない」といった症状はありませんか?
多くの方は季節の変わり目の風邪と思われるのではないでしょうか。
しかし、もしこうした症状が1,2週間と続くようならマイコプラズマ肺炎の可能性も。今回の記事ではマイコプラズマ肺炎の症状、自分でできる対策・予防に必要な栄養素について、国際オーソモレキュラー医学会会長の柳澤先生に監修いただきご紹介していきます。
マイコプラズマ肺炎とは?
どんな症状?
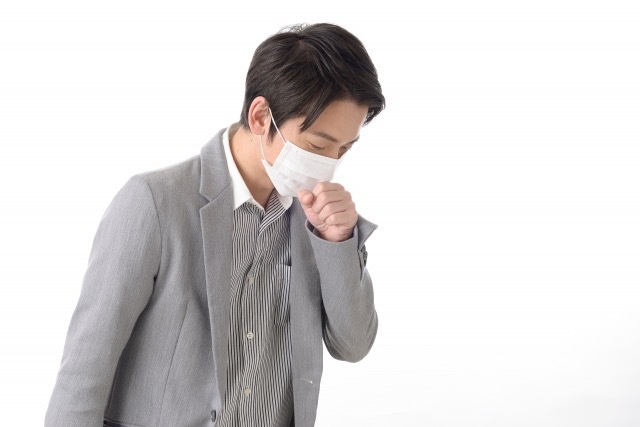
マイコプラズマ肺炎は2,3週間ほどの長い潜伏期間を経て様々な症状を引き起こします。
まず初期症状として挙げられるのは発熱、頭痛、倦怠感。これらの症状は風邪とよく似ているため、見極めにくいのが正直なところ。もし長引く発熱に加え数週間乾いた咳が止まらない、もしくは咳の症状が悪化するようであれば、マイコプラズマ肺炎の可能性もあります。
上記以外の症状としては以下のようなものが挙げられます
- 声のかすれ
- 呼吸困難
- 吐き気等の消化器症状
- 耳や喉の痛み
- 胸痛
- 関節痛
マイコプラズマ肺炎に感染していた場合でも、これら全てにあてはまるとは限りません。いくつかの症状に当てはまる場合は放置せず、なるべく早めに医療機関を受診しましょう。
合併症を引き起こす可能性も
マイコプラズマ肺炎は重症化することが少ないといわれています。しかし、適切な治療が遅れてしまうと思わぬ合併症を引き起こしかねません。
マイコプラズマ肺炎の症状が重くなることで起こる可能性のある合併症には…
- 中耳炎
- 関節炎
- 消化器症状(下痢、嘔吐)
- 脳炎
- 心筋炎
- 無菌性髄膜炎
- ギラン・バレー症候群
…などが挙げられます。
また、喘息もちの子どもの場合には、喘息症状が悪化することもあります。
予防法

風邪と似た症状が多く、なかなか判断が難しいマイコプラズマ肺炎。現時点では、マイコプラズマ肺炎に対する予防ワクチンはありません。それでは自分でできる対策としては、どのようなことがあるでしょうか。
手洗い・うがいを徹底する
マイコプラズマ肺炎に限らず、飛沫感染・接触感染する病気から身を守るためには、基本的な手洗い・うがいが肝心です。忙しいとつい手早く済ませがち・・・という場合も多いかもしれませんが、できる限り丁寧に行う習慣を身につけられるといいですね。人混みのなかを歩く時はマスクを着用するなど、日頃からウイルスへの感染予防を意識することが大切です。
しっかり睡眠時間をとる
疲れを溜め込むと免疫力は落ちてしまうもの。免疫が下がると病原菌への抵抗力も弱まってしまいます。多忙な毎日を送っている人は特に睡眠時間を多めに確保できるように心がけましょう。
バランス良く栄養補給
睡眠時間とともに大切なのがバランスの取れた食事。コンビニ食・ファストフードを食べることや朝食を抜くことが多い場合、栄養素が全体的に不足しがちになります。そうでなくとも1日3食のなかから全ての栄養を補給するのは、なかなかハードルが高いですよね。
そんな時には、気軽に摂取できるサプリメントで補うのがおすすめ。足りない栄養素を食事にプラスしてサプリメントで付け足していけると効果的です。
マイコプラズマ肺炎の予防として特に摂取しておきたい栄養素を先生に伺いました。
【ビタミンD】
ビタミンDは免疫機能を調整する役割を担っています。不足するとインフルエンザや肺炎などの感染症にかかりやすくなると言われています。
また、日光を浴びることでビタミンDは体内生産されるので、休日は外に出て日光浴を楽しんでみては?心も体もリフレッシュできますよ!
<ビタミンDを多く含む食品>
さけ、しらす、卵黄、きくらげなど
【ビタミンC】
ビタミンCには抗酸化作用があり、病気を促進する活性酸素から私たちの体を守る働きがあります。多く摂取することで、より高いウイルス対策効果が期待されます。ビタミンCは体内で合成することができないため、効果を実感するには毎日の補給がポイントとなるとのこと。
<ビタミンCを多く含む食品>
野菜では赤・黄ピーマン、芽キャベツ、パセリ
果物ではアセロラ、レモン、ゆずなど
まとめ
1.png)
ただの風邪と思って放置した結果、思わぬ病気を招く危険性も。もし長引く咳や発熱がある場合は、早めに医療機関へ相談することが早期回復のポイントです。日常的にバランス良く栄養を補給し、睡眠時間を多くとることはあらゆる病気への免疫力を高めます。
自分に足りていない栄養素が何なのかわからない・・・とお悩みの方は、栄養療法を行っている専門機関での検査を行ってみては?と柳澤先生。自分の今の体の状態を知るきっかけにもなります。
<出典>
毎日新聞『ビタミンD:肺炎、インフル発症2割減 国際チーム研究』
https://mainichi.jp/articles/20170413/k00/00e/040/233000c
柳澤 厚生 (ヤナギサワ アツオ)先生の関連動画
同じタグの記事を読む
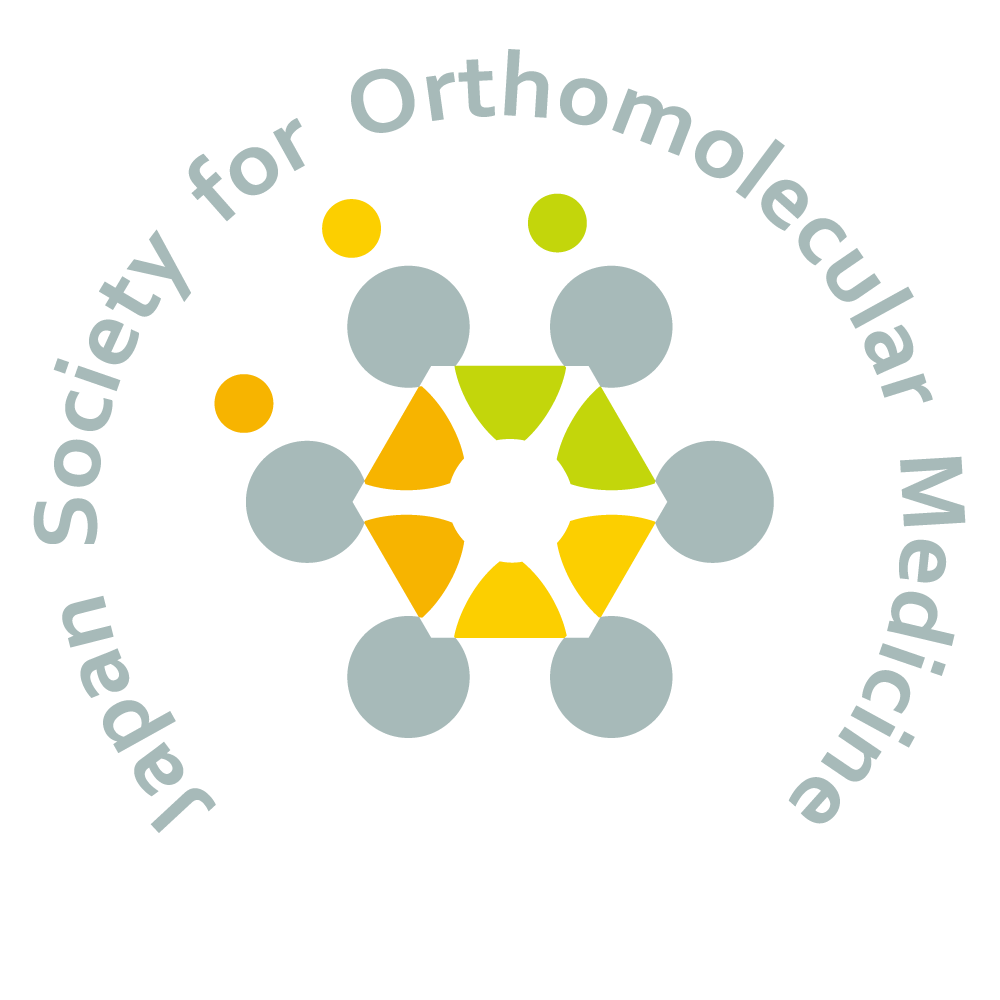

のコピー1.jpeg)