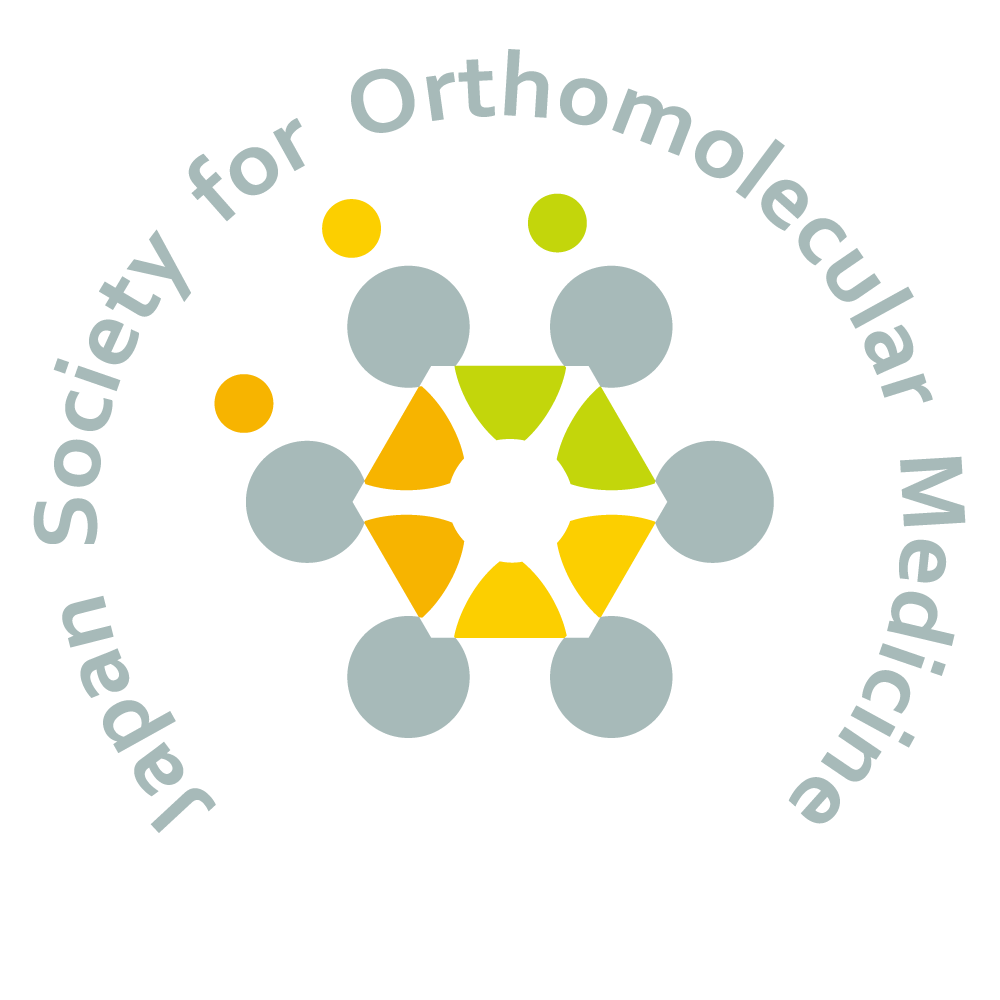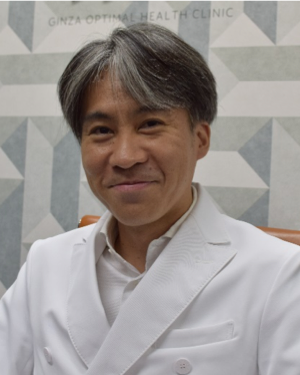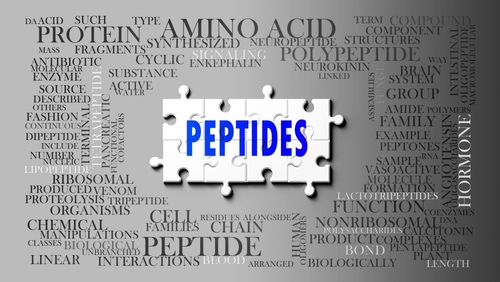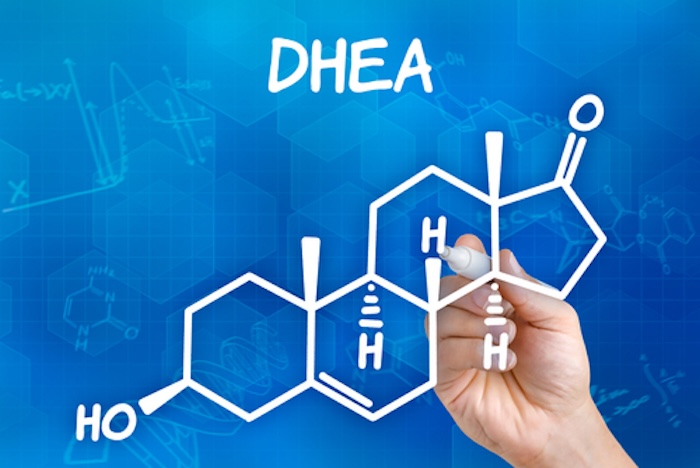体重と体脂肪を減らすダイエット。その基本は「消費カロリー>摂取カロリー」と考えられています。これは、はたして正しいのでしょうか?大量にカロリーを摂っても太らない人もいれば、ほとんど食べていないのに太ってしまう人もいます。同じ人物が同じ食事をしたとしても、ある時期は太りある時期は痩せるといった現象も起こります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
- 悩み・目的
- 治療法・栄養
リバウンドが怖い人にこそ勧めたい「ローカーボダイエット」

世間には様々なダイエット法が存在しますが、いずれのダイエットにおいても大敵はリバウンドでしょう。リバウンドせずに余分な脂肪を落とすのが理想的なダイエット法と考えるなら、一番の近道は「ローカーボダイエット」です。
ローカーボダイエットのポイントは糖質摂取を減らし脂質摂取を増やすということで、そのためには脂質を効率よくエネルギーに変換する必要があります。体内をケトーシスの状態に持っていき、ケトン体をエネルギー源にできる体にすることがカギとなります。糖質制限、解糖系※1 を阻害する食べ物の摂取、十分な脂肪の摂取(特にアセチルCoAができやすい脂肪)を意識することで、ケトーシスへの移行をスムーズにします。
さらに、上手にサプリメントを活用することでより効率良く脂肪を燃焼させ、リバウンドを起こさずに痩せることができます。
※1:ブドウ糖をピルビン酸もしくは乳酸に分解する反応。
「カロリー神話」の崩壊
体脂肪についての説明は簡単です。摂取カロリーが消費カロリーを300kcalオーバーしたとしても、それが筋肉になったのであれば体脂肪は増えません。体重が全て筋肉として増加した場合、増えるどころか体脂肪率はむしろ低下します。オーバーしたカロリーが全てグリコーゲンとして蓄えられた場合も同様です。
一方、体重については少々複雑な話となります。摂取カロリーが300kcal増えたからといって、そのまま肉体になる訳ではありません。また、消費カロリーが300kcal増えたからといって、全て肉体からなくなる訳でもないのです。これは、人体では「質量保存の法則※2」が成り立たないことによるものです。人体は開放系ですが、質量保存の法則が成り立つのは閉鎖系です。開放系では周囲とのエネルギー(仕事・熱)のやり取りができ、物質の移動も可能となります。
※2:ある化学反応の前後において、物質の総質量は変化しないという法則。
タンパク質は絶対量で考える
糖質はエネルギー源、タンパク質は体の構成成分、脂肪はエネルギー源、エイコサノイド※3の材料となります。各々の役割を考えると、それぞれの「バランス」よりもそれぞれの「量」が重要になってきます。特に、絶対量で考えるべき代表とも言えるのがタンパク質です。主にエネルギーとなる糖質や脂肪は体脂肪や筋肉などの分解で代用が可能ですが、タンパク質は代用できません。
では、タンパク質の絶対量はどれくらいに設定すべきでしょうか?この絶対量の目安については、トレーニングしている人とトレーニングしていない人で変わってきます。トレーニングしている人で体重1kgあたり2~2.5g、トレーニングしていない人では体重1kgあたり1~1.5gが推奨されます。(ただし腎臓が問題ない方に限ります)
ローカーボダイエットを行う際は、糖質10%:タンパク質30%:脂質60%のカロリー比を目安に取り組むと良いでしょう。
※3:プロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエンなどの生理活性物質の総称。
ローカーボダイエットを成功させる秘訣
ローカーボダイエットが上手くいかない理由の大半は、十分量の脂肪が摂れていないことにあります。ローカーボ実施時のポイントはケトン体をエネルギーに変えることです。このケトン体の材料となる脂肪の摂取量が足りないと、糖新生※4が亢進して筋肉の分解が進んでしまうのです。
※4:主に血液中のグルコースが不足している時、糖質以外の物質(アミノ酸など)からグルコースを生成すること。
良質な脂肪源となるキーフード
せっかくローカーボダイエットを始めたのならば、上記のような事態は避けたいものです。ここで、効率良く脂肪を摂取できる代表的な食材をいくつかご紹介します。
①アボカド
1日1個のアボガドをおすすめします。アボガドには1個あたり30g以上の脂肪が含まれています。脂肪酸は主にオレイン酸が中心でビタミンEも多く、タンパク質も5gほど含まれます。1日1個のアボガドを食べたところ、コレステロール値が改善されたという報告や、メタボリックシンドロームのリスクが低下し、ダイエットの質が向上したという報告もあります。
②肉類
タンパク源としてサーロインステーキや全卵、青魚を食べるようにすれば、同時に脂肪も摂取できます。飽和脂肪酸の健康に対する悪影響を心配される人もいますが、2010年に発表された35万人を対象としたメタアナリシスにおいて、飽和脂肪酸摂取量と脳や心血管イベントの発生には関連がないことが明らかにされています。
また、2015年の論文でも上記と同様のことが示されており、ここでは飽和脂肪酸ではなくトランス脂肪酸の問題が示されています。豚肉(特にイベリコ豚)はオレイン酸含有量が多く、全体の半分ほどになります。
③ナッツ
ナッツには様々な効果が期待できます。代表的な作用としては、下記が挙げられます。
- 血圧を下げ、心血管系の合併症を予防する
- 慢性腎臓病による死亡率を低下させる
- 体重減少作用
- メラニン生成抑制作用
④MCTオイル
糖質制限時は1日30g程度を目安に。お腹が緩くなることもあるので、徐々に増やしていくことを推奨します。
※MCTオイル・・・中鎖脂肪酸(ココナッツなどに含まれる)のみを取り出した食用油のこと。
飽和脂肪酸=“悪”という誤解
2017年、『ランセット』に発表された18カ国の13万人を対象にした追跡調査では、「高炭水化物の食事は総死亡率を高める。脂肪摂取量が多いほど総死亡リスクは低くなる。飽和脂肪酸の多い食事は脳卒中のリスクを減らす。総脂肪摂取量や飽和、不飽和脂肪酸の量は心血管系疾患による死亡率と関連しない」と結論付けられています。
当時、これはかなり衝撃的な発表でした。ランセットという世界的に有名な医学雑誌に掲載されたことも相まって、多くの議論を呼びました。「飽和脂肪酸は悪玉」というそれまでの常識が覆されてしまったのです。
ケトーシスになりにくい場合の対策
ケトン体をエネルギーに変換できている状態をケトーシスと呼びます。ケトーシスになるとエネルギーを確保できるため眠気や疲労感も解消され、糖新生も起きにくくなり、筋肉の分解も減少していきます。しかし、ケトーシスの状態になかなかなれずに糖質をエネルギー源としたまま糖質が制限されると、ただの“エネルギー不足”となってしまいます。その結果、疲労感や空腹感に襲われ、糖新生も亢進、そして筋肉の分解も進んでしまいます。
ケトーシスになるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 糖質を減らし、ピルビン酸ができないようにする→食事制限
- ピルビン酸の産生を抑えるため、解糖系を阻害する→シリマリン、ゲニステイン、ケルセチンの摂取
- 十分な脂肪を摂取し、アセチルCoAが大量にできるようにする→食事制限
- アセチルCoAができやすい脂肪を摂取する→MCTオイル、ココナッツオイル
ケトーシス移行のためのサプリメント
最後に、ケトーシスになるために役立つサプリメントをご紹介します。
- αリポ酸:300mgずつ毎食後、1日900mg。R型の場合は100~200mgずつ1日300~600mg。
- アルギニン:1日9g (1回3gを3回)。
- ケルセチン:1日1500mg(毎食後500mgずつ)
- EPA:青魚をよく食べる場合は必要なし。そうでない場合は、EPA+DHAとして1日2000mg以上。
- バナバ茶:毎食時に飲む。
これらにビタミンB2、カルニチン、CoQ10を加えるとさらに良いでしょう。
<参考文献>
・『ダイエットの理論と実践』(山本義德 著, NextPublishing Authors Press,2019)
同じタグの記事を読む