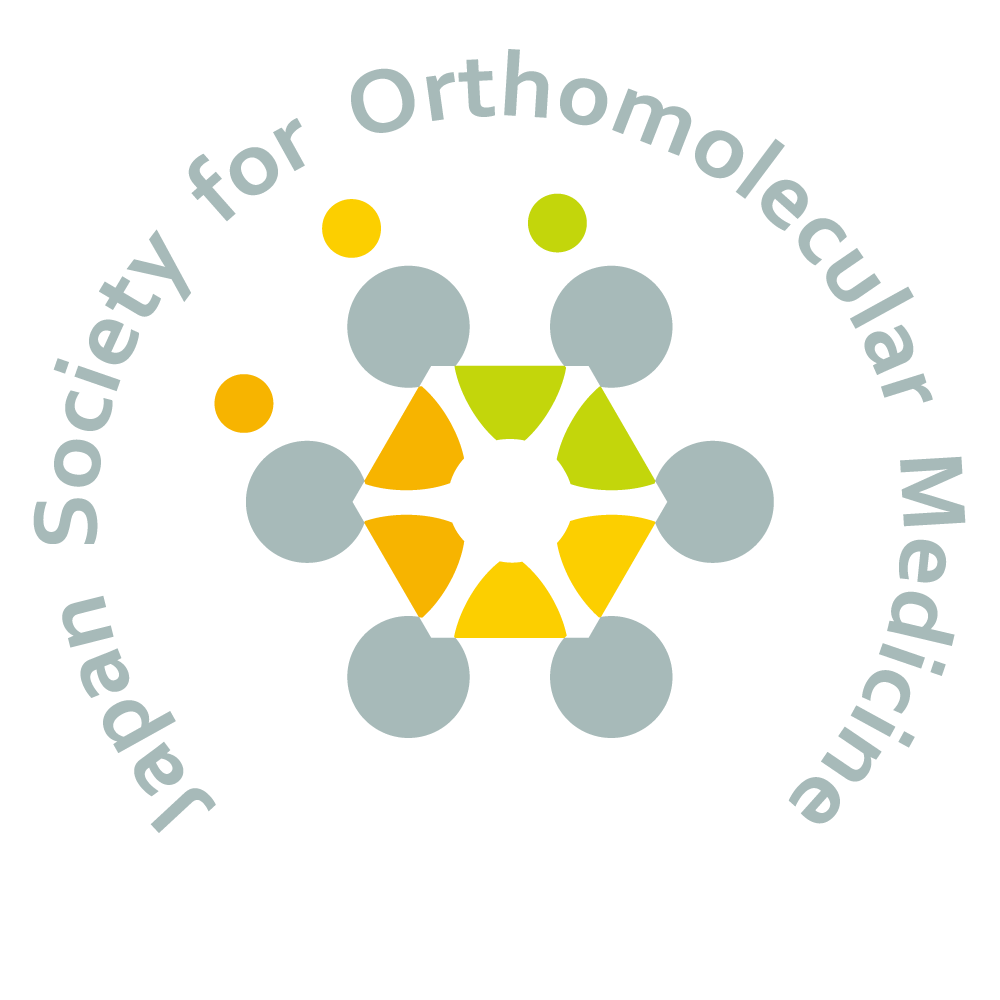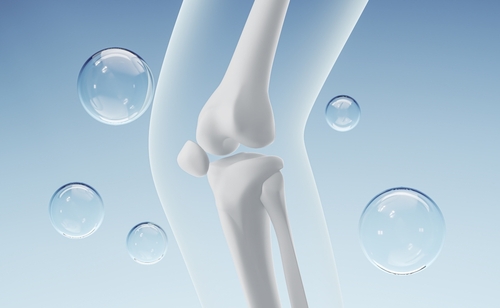がん細胞は発生時から老化による変質と免疫機構の機能低下という問題を抱えているという新たな認識が広がることで、おそらく、従来のがん免疫治療アプローチにも一定の戦略変更が論じられることでしょう。たとえば、現在でも自由診療において、NK細胞や樹状細胞など多様ながん免疫療法が提供されています。最近では、新たな治療対象としてマイクロRNAやエクソソームなども注目され、免疫治療の選択肢も増えつつあるのが実情です。
がんと免疫治療

〜新たな視点の始まり〜
21世紀に入り、徐々に「がんは炎症性老化によって生じる疾患群の一つ」という考え方が広まってきました。それまで、がん細胞の驚異的な増殖能力を目の当たりにした人々は、何らかの形で「若々しさ」を超越した細胞であるとのイメージを重ねていたことでしょう。
しかし、老化に関する研究が進展するにつれ、遺伝子DNAの変異によって生じたがん細胞が、実は「無秩序な老化状態」に陥っていること、そして、対抗する免疫機構にも老化性の機能障害が及んでいることが判明し始めます。つまり、がん細胞は発生当初から老化による変質と、それに対抗する免疫機構の機能低下という問題を抱えていたのです。
そして、こうした病態ががん細胞/免疫機構の双方に影響を与える老化性変化によるものだと明らかになるまでに、そう長い時間は必要ありませんでした。
そうした経緯を経て、がん免疫治療の戦略を考える際には、「老化」という側面も考慮する必要があることに、一部の臨床医らが気づき始めたのです。言い換えれば、単に免疫機構を活性化させるだけでは根本的な解決に至らない、という認識が次第に広がりつつある証左といえるでしょう。
本稿では、がん免疫治療の実践にあたり、その焦点となる細胞の「老化性変化」と、その改善に向けた源流対策について述べるとしましょう。
新たな免疫治療の方向性
さらに、保険診療での標準治療にも採用されている免疫チェックポイント阻害剤も、特定の免疫プロセスに対する治療薬として位置づけられています。もちろん、私もこれらの治療手法を否定するものではありません。とは言え、がんの老化性環境という問題を考慮に入れると、がん細胞/免疫応答の根本的な解決策となる源流対策も必要であろうと考えます。なぜなら、例え優秀ながん免疫治療であったとしても、がん腫瘍/免疫システムの相互認識が成立しない限り、その効果は限定的となってしまうに違いないからです。
がんと免疫:複雑な相互関係
免疫システムの基本的な役割は、「自身のもの(自己)」と「それ以外(非自己)」を見分け、後者を排除することにあります。しかし、がん診療の現場では、こうした単純なプロセスが必ずしも通用しないケースが多々見受けられます。あえて放言するなら、備わった免疫システムが十分に働かないのが、がん治療をとりまく一般的な実情と言えるでしょう。
それでは、なぜ、体内に発生したがん細胞には免疫機構が適切に応答しないのでしょうか。この問いに対する一つの答えが、R. D. Shreiberらによって提唱された「がん免疫編集」という概念にありました。本稿でのテーマではありませんが、がん免疫治療において非常に重要な考え方であるため、少しだけ触れてみることにしましょう。
がん免疫編集からみた、がん免疫治療の新たな視点
がん免疫編集は、がん細胞の発生からがん腫瘍の形成までを以下3つの段階として解説がなされています。
<排除相>
正常なDNAに変異が蓄積すると、がん細胞の発生リスクが高まります。この段階になると、通常DNAの修復機構が即座にこの変異に対応しますが、機会を逃してしまうこともあり得ます。その場合には、マクロファージやナチュラルキラー細胞(NK細胞)が、がん細胞の排除を担当にあたります。
この段階では、がん細胞の「免疫原性が高い」という未編集の免疫環境により、「がんらしさ」を保持できていることが特徴です。
<平衡相>
この段階になると、がん細胞は変異遺伝子によって様々な「がん関連抗原(TAA:オンコアンチゲン)」や、「がん特有抗原(TSA:ネオアンチゲン)」を合成し始めます。それによりがん細胞は、高い免疫原性を持つペプチドによって排除される場合と、免疫編集によって低い免疫原性に変化したペプチドの影響で逃避してしまう場合の二通りが存在します。
がん免疫治療の観点でこの時期を判断したなら、がん細胞と免疫応答が平衡状態を保つ可能性を充分に秘めた、理想的な治療目標の姿であるとも解釈できるでしょう。
<逃避相>
この段階に達するとがん細胞は急激に増殖し、明確な腫瘍を形成し始めます。この時点でのがん細胞の特徴は、「ホット・テューモア(hot tumor)」(※1)と「コールド・テューモア(cold tumor)」(※2)、あるいは、その中間的な性質を持つものに分けられることです。
※1 ホット・テューモア: このタイプでは逃避相に至っても免疫応答は維持され、腫瘍内への多数のキラーT細胞浸潤とともに、免疫チェックポイント阻害剤が奏功しやすいという特徴があります。
※2 コールド・テューモア: このタイプでは免疫応答もほぼ失われて腫瘍内へのキラーT細胞浸潤も非常に少なく、免疫チェックポイント阻害剤の効果が得られないという特徴があります。そのため、MHCを介さずに腫瘍を排除するCAR-T細胞療法などの臨床応用も検討されています。
MHCとがん免疫治療:がんとの闘いの鍵
ここでは、前述の平衡相と逃避相において、がん免疫治療の成果を生むための基盤となる要素、MHC(Major Histocompatibility Complex)について説明します。
MHCは、HLA(Human Leukocyte Antigen)とも呼ばれ、細胞表面でT細胞に識別情報を提供する微細な複合体を形成します。その表面には抗原ペプチドを載せるための小さな窪みがあり、MHCと抗原ペプチドが結合して細胞表面に現れることで、T細胞がその細胞を識別するためのマーカーとして機能するのです。
さらに、MHCにはClass I(※3)とClass II(※4)の二つの型が存在し、それぞれが異なる情報伝達の役割を果たしています。
※3 MHC-Class I:多くの細胞表面に存在し、細胞内の状態をキラーT細胞に伝える識別マーカーの役割をしています。
※4 MHC-Class II:主に樹状細胞の表面に現れ、他の免疫細胞が処理したペプチドを伴って、ナイーブT細胞に情報を提供する役割をしています。
MHCの存在ががん免疫治療の成果にどう影響するかというと、T細胞の受容体(TCR)とMHCペプチド複合体の相互作用が免疫応答のトリガーとなるからです。特に、この複合体のペプチドががん由来であれば、T細胞はその細胞をがん細胞と断定し、免疫応答によって破壊したのちに体外へと排除します。
ただし、すべてのがん細胞がMHC複合体を表面に発現するわけではありません。がん細胞の増殖に伴った老化の進行が著しいと、MHCの合成が妨げられる場合もあるからです。その結果、がん細胞内で生成される抗原も、MHCと結合して細胞表面に現れることができなくなってしまいます。
このような問題に対処するため、私たちの医療施設では、がん細胞内のMHC合成が滞っている場合に、その再合成を促進する「MHCペプチド誘導」という治療を積極的に取り入れています。
がんの治療の真の意義とは
いかがでしたでしょうか。こちら日本オーソモレキュラー医学会に用いられた名称、"Orthomolecular"は、主に「正常分子」または「整分子」と訳されることが多い用語であること。そして、言い換えると栄養素やビタミン、ミネラルなどの分子を体内で「正常な」レベルに保つことで、健康を維持・改善するという考え方に基づくものと解釈させていただきました。
私たちの医療施設でも、がん免疫治療の成果を最大化するため、「自己」と「非自己」の識別に不可欠なMHC複合体「分子」の最適化に力を入れている点で、その着想は"Orthomolecular"に近いものと考えます。そして、その診断基盤に活用しているのが、初診時に必ず行う「リスクチェッカー」と呼ばれるがん免疫/大規模AI解析システムです。
当院を訪れるそれぞれの患者さんが抱えるご病状は多岐にわたります。特に、高度進行がんを主要な治療対象としているため、免疫疲弊や炎症性老化の程度を示すサイトカイン指標や免疫細胞の各種指標、多種のがん抗原検査は欠かせません。こうした検査結果を踏まえ、パーソナライズされたがん免疫治療を提供することで、患者さんに免疫応答の改善が見られることも決して少なくはないのです。
最後に
そして、最後にこの場をお借りして、自由診療型としてのがん免疫治療を実践する上で配慮すべきもう一つの重要なポイントについてお話させていただきます。それは、患者さんが過去にどのような医療を受け、特に標準治療での成果がどうだったかを詳しく調査することです。特にこの点が気になりだした背景には、近年の高度進行がんに対する治療方針がどうも悲観的な方向にシフトしているような気がしてならないからです。
例えば、ありがちな患者さんへの応対として、「もう、~無い」という言い回しがあります。おそらく、「もう、実施する治療が無い」「もう、入院していてもやることが無い」といった風に多用されるのでしょう。なぜ、「まだ、~ができるはずだ」「まだ、~の可能性が残っている」、といった風の前向きな対応がなくなってしまったのでしょうか。
私が一外科医として医業を開始した1986年当時は、がん治療や手術に情熱を注ぎ、常に「まだ、何ができるか」を探求する日々でした。もちろん、当時は、「がんは老化性疾患である」といった考え方も存在しませんでしたが、今になってその時代の真剣な取り組みがいかに貴重であったかを懐かしくも痛感する毎日です。
同じタグの記事を読む