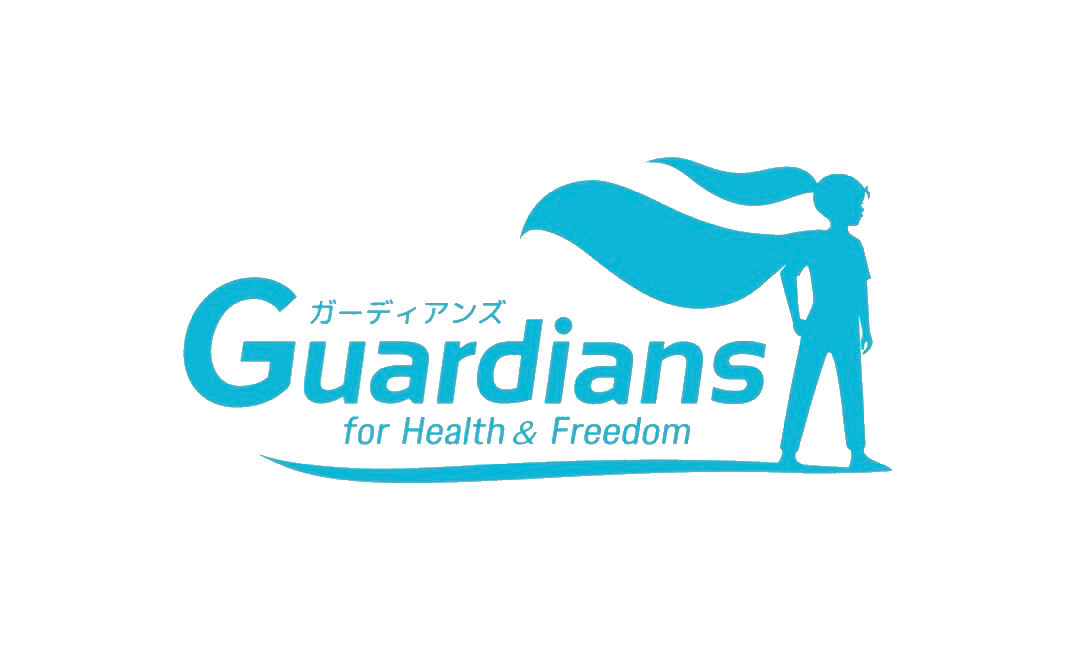免疫力は生まれながらに持つ体の力で、病気を治す「自然治癒力」と病気を予防する「抵抗力」があります。これらの働きを支えるのが「自律神経」です。自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があって、このバランスが崩れると免疫力が弱まってしまいます。
- 治療法・栄養
食生活の見直しで免疫力を高める!玄米などおすすめ食材を紹介
.png)
病気の予防を考えるときに注目したいのが「免疫力」。免疫力が弱まると風邪をひくというイメージがある人もいらっしゃるかもしれません。ただ、実際に免疫力を高めようと思ったときに、何をしたらいいかよく分からない人も多いのではないでしょうか。今回は免疫力を高めるために、自分でできる食生活の見直しについて、国際オーソモレキュラー医学会会長の柳澤先生に伺ってきました。
免疫力を高めるポイントは「副交感神経」
ストレスが多く慌ただしい現代社会では、活動を司る「交感神経」に傾きがちで、バランスが崩れやすくなっています。休息を司る「副交感神経」をいかに優位にする食べ方ができるかというのが、免疫力を高める1つのポイントになってきます。
副交感神経を優位にするためには
副交感神経を優位にする食事ができれば、緊張していた交感神経がゆるみ、血管が拡張して血液の流れもよくなり、病気の予防・治療にも役立ちます。では、具体的にどこに気をつけたらいいのでしょうか?
例えば、下記のような作用を持つ食べ物を食べるのが良いとされています。
- 腸の働きを活発にする
- 体を温めて血行をよくする
- 便通を高める
自律神経のバランスを整える「穀物」も重要
.png)
食べ物には交感神経・副交感神経それぞれを刺激する特徴があります。例えば、脂っこい食べ物や冷たい食べ物は、交感神経の働きを刺激するため、摂りすぎると免疫力の低下につながるのです。
どちらの神経にも偏らない「中間の食べ物」もあります。それが白米・玄米・小麦・芋類などの穀物です。この辺りを食事に取り込むことが、神経のバランスを保つために重要になってきます。今回は特に、栄養面でも優れる「玄米」について紹介します。
「玄米」は免疫力アップに効果的!
病気の予防や治療に役立つ食品の1つが「玄米」です。玄米の胚芽部分とぬか層には特に栄養が豊富です。白米に比べて、食物繊維・ビタミンB1ビタミンEは実に4倍、ビタミンB2・鉄やリンなどのミネラル類は2倍も含まれているのです。
また、玄米は硬いので、よく噛む必要があります。栄養バランスのいい玄米をよく噛んで食べることで、過食を防ぎながら副交感神経を優位にして免疫力を高めることができます。玄米は、病気になった時や老化が気になり始める時期に食べるのが、特におすすめです。
その他、免疫力を高める食事とは?
.png)
穀物以外には、どんな食事を選ぶべきなのでしょうか?副交感神経を優位にするためにおすすめの食材にはこんなものがあるそうです。
植物性食品(かぼちゃ・さつまいも・バナナなど)
- 体内でエネルギーを作る細胞の小器官・ミトコンドリアの働きを高めるカリウムや植物性たんぱく質、ポリフェノールなどを多く含みます。
発酵食品(チーズ・納豆・味噌など) - 発酵の家庭でできる酵素がそれぞれの原料と作用して副交感神経を優位にします。さらに、腸内環境を整えて免疫力を高めます。
食物繊維が多い食品(きのこ・海藻など) - 食物繊維は腸管を活発にして、副交感神経を優位にしてくれます。また、便通を高めて体内の毒を出す効果もあります。
全体食品(穀物・大豆など) - 玄米もここに含まれます。多くの栄養素や生命エネルギーを含むので、病気の予防や回復に役立ちます。
すっぱい・苦い・辛い食品(ピーマン・梅干し・ゴーヤなど) - すっぱい・苦い・辛いなどの食品は副交感神経を刺激して免疫力を高めます。また、殺菌効果や排泄を促す効果もあります。
体を温める食品(にんにく・しょうが・ニラなど) - 血流を促して副交感神経を優位にし免疫力を高めます。新陳代謝もよくなるので、美肌効果も。
毎日の食事に気をつけることが、免疫力を高める第一歩になります。こうした食材を、うまく取り入れていってみましょう
ストレス食いや過食には注意!
副交感神経はリラックスする時に刺激されます。いくらバランスの良い食事を食べても、食べ過ぎてしまったり仕事をしながら食べたりしたのでは、リラックスできず副交感神経を刺激することはできません。楽しんで美味しく食べること、それも免疫力を高める方法の1つになります。
バランスのいい食事を第一に、必要に応じてサプリメントも
みなさんの食生活と照らし合わせて、これらの食材は取り入れられていましたか?もしまだ改善できそうでしたら、ぜひ食生活の見直しで免疫力を高めていきましょう。
ただし、毎日の食事に全てを取り入れるのは難しいかもしれません。1つからでも構いませんので、少しずつ気をつけていくことが、長続きのコツになってきます。
また、忙しくてあまり食事に気をつけることができない場合には、必要に応じてサプリメントなどで栄養を補充するのも効果的です。サプリメントは、自分の体調や体質に合った、品質のいいものを選ぶことが重要です。何を飲んでいいか分からない場合は、ぜひお気軽に専門医に相談してみるのがおすすめですよ。
冬に気をつけたい「インフルエンザ」予防に必要な栄養素はこちらの記事で紹介しています。
インフルエンザ予防に必要な5つの栄養とは?
【参考文献】
「安保徹が教える免疫力を10倍高める食べ方」(永岡書店、2015年)
柳澤 厚生 (ヤナギサワ アツオ)先生の関連動画
同じタグの記事を読む
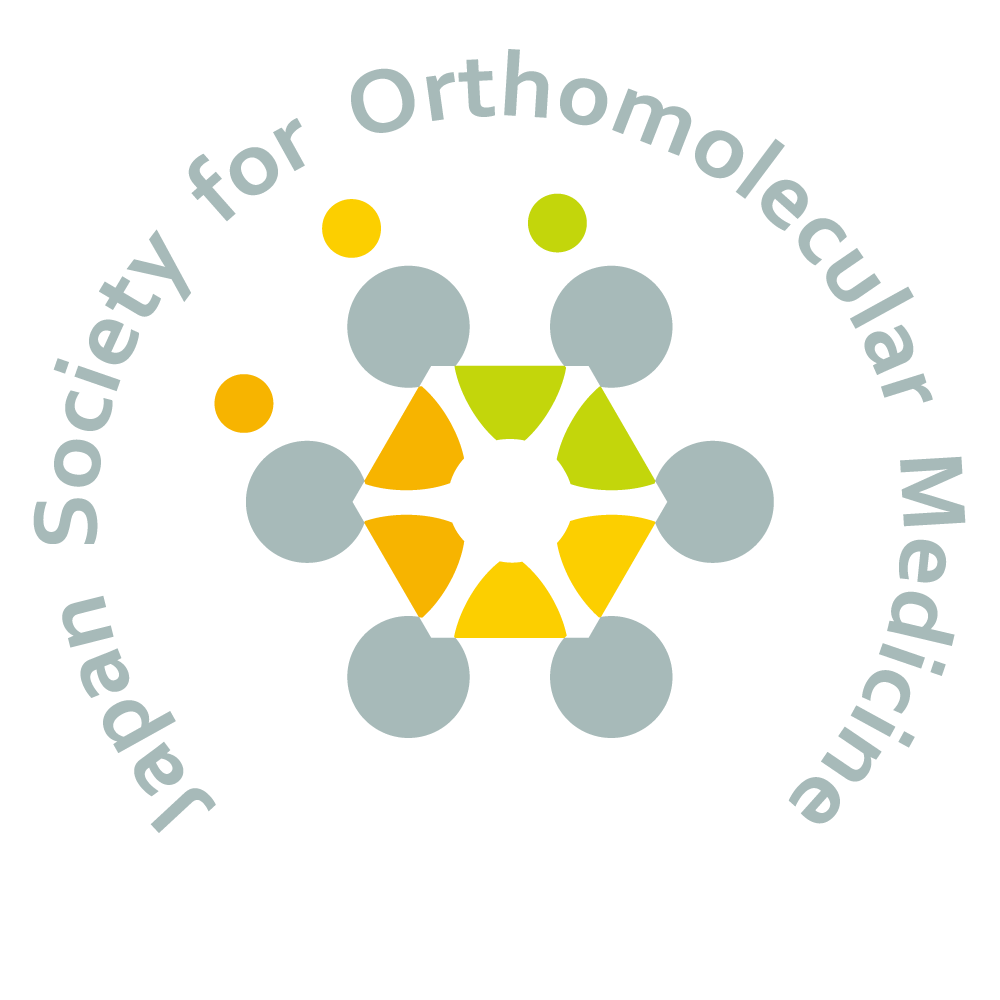

のコピー1.jpeg)